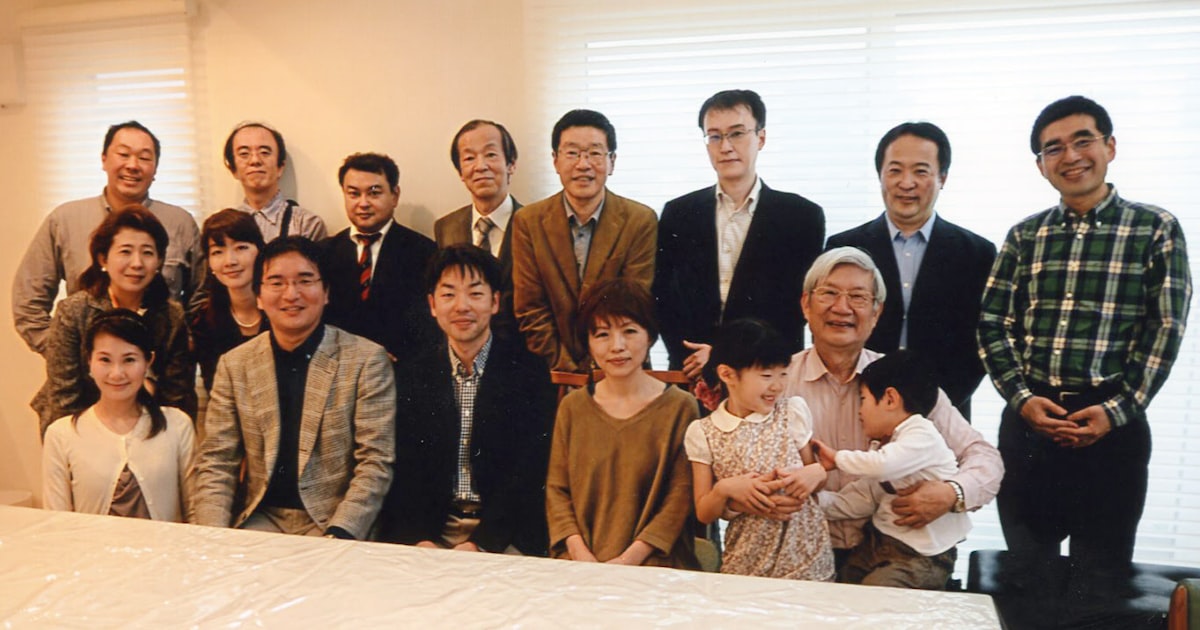Events 近況
2019年12月
12月1日、NHK報道特番「中曽根康弘元首相と戦後日本」に出演しました。
司会者は伊藤雅之解説副委員長、出演者は藤崎一郎大使、御厨貴先生、私でした。
こちらにリンクを貼っておきます。
2019年11月
『中曽根康弘――「大統領的首相」の軌跡』(中公新書、2015年)が電子書籍になりました。
こちらにリンクを貼っておきます。
一部に加筆修正してあります。
2019年10月
拙著『増補版 大平正芳 理念と外交』(文春学藝ライブラリー、2019年)が刊行されました。
『大平正芳 理念と外交』(岩波書店、2014年)の増補版です。
解説については、御令孫の渡邊満子様が執筆して下さいました。
Kindle版については、こちらを参照していただければ幸いでございます。
関係各位に深謝申し上げます。
なお、『大平正芳 理念と外交』(岩波書店、2014年)は、以下のように中国語訳されています。
服部龍二/沈丁心・騰越訳/郭連友校『大平正芳的外交与理念』(北京:中央編譯出版社、2017年)
いつの間にか、Kindle Unlimitedで\0.00になっていることに気づいてしまいました。
2019年9月
拙著『増補版 大平正芳 理念と外交』(文春学藝ライブラリー、2019年)を進めています。
10月に刊行予定です。
2019年8月
『日本歴史』8月号に拙著『高坂正堯――戦後日本と現実主義』(中公新書、2018年)の短評が掲載されました。
歴史系の学会誌に取り上げていただけるとは、思っておりませんでした。
関係各位に深謝申し上げます。
2019年7月
前期の授業が終わりました。
これから期末試験の採点やレポートの添削を行います。
また、Ryuji Hattori, translated by Tara Cannon, Understanding History in Asia: What Diplomatic Documents Reveal (Tokyo: Japan Publish Industry Foundation for Culture, 2019) につきまして、Japan Libraryの方々が海外に発送して下さいました。
同書は、Kindleでも読めるようになりました。
こちらにリンクを貼っておきます。
関係各位に深謝申し上げます。
2019年6月②
拙稿「30年ルールの起源と外交記録公開」(『外交史料館報』第32号、2019年3月)が、外務省ホームページに掲載されました。
こちらにリンクを貼っておきます。PDFで開きます。
2019年6月
拙稿「岡崎嘉平太と中国」(『中央大学論集』第40号、2019年2月)が、中央大学学術リポジトリに掲載されました。
こちらにリンクを貼っておきます。
2019年5月
戸部良一先生「時評 恩師の評伝 服部龍二『高坂正堯』を読む」(『アステイオン』第90号、2019年5月)を拝読いたしました。
「『御用学者』という批判は、『タレント教授』という中傷と同じく、歯牙にもかけなかっただろう」といった御指摘や、学長就任予定だった静岡文化芸術大学に関する「お年寄りがいつでも出入りできて、若い人と交流できるようにするんや」という高坂先生の言葉が印象的でした。
同号の特集や連載なども、拝読させていただきました。
2019年4月②
拙稿「30年ルールの起源と外交記録公開」(『外交史料館報』第32号、2019年3月)が公表されました。
いずれ外務省のホームページに掲載されると思います。
こちらにリンクを貼っておきます。
このテーマについては、将来的にまとめられればと考えております。
また、同稿の公表をもちまして、日本外交文書編纂委員会委員を退きました。
2012年から7年間、外交史料館では大変にお世話になりました。
編纂室、編纂委員会をはじめ、関係各位に深く御礼を申し上げます。
あまりお役に立てず、忸怩たる思いです。
2019年4月
新学期が始まりました。
今日は、教員紹介など新入生との交流会がありました。
また、しばらく大学を離れていたため気づくのが遅れましたが、年度末に学外の方々から、何冊か御著書を贈っていただきました。
誠にありがとうございます。
本来であれば、拝読のうえ返礼すべきところなのですが、それが難しくなっており、申し訳ありません。
2019年3月
Ryuji Hattori, translated by Tara Cannon, Understanding History in Asia: What Diplomatic Documents Reveal (Tokyo: Japan Publish Industry Foundation for Culture, 2019) が刊行されました。
Japan Libraryの1冊です。
関係各位に深く御礼を申し上げます。
同書は、拙著『外交ドキュメント 歴史認識』(岩波新書、2015年)の英訳です。
『外交ドキュメント 歴史認識』については、第2刷で4頁ほど加筆してあります。
その加筆は、英訳に反映されています。
2019年2月③
「岡崎嘉平太と中国」(『中央大学論集』第40号、2019年2月)が公表されました。
「岡崎嘉平太と中国」(岡山県郷土文化財団岡崎嘉平太記念館『日中国交正常化40周年記念 岡崎嘉平太がめざした世界平和への道を考える 第11回 講演会』岡山県郷土文化財団岡崎嘉平太記念館、2013年1月)に加筆修正したものです。
いずれPDFが、中央大学学術リポジトリに掲載されると思います。
こちらにリンクを貼っておきます。
2019年2月②
五百旗頭真「私の履歴書(16)神戸大のゼミ 長時間の真剣勝負 光る若い感性」(『日本経済新聞』2019年2月17日朝刊32面)を拝読いたしました。
こちらにリンクを貼っておきます。
そのなかに、次のようなくだりがあります。
ある私立女子大へ非常勤で出講したところ、出席が義務で、興味なき者も全員が大教室にひしめき、私語をする。沈黙させる方途を見いだすのに何カ月も要した。
興味をもってもらうのに思案したという意味では、私にも似たような経験があります。
近年では私語よりも、スマホに没頭する学生さんが多いようです。
そこで授業が飽きられないように、ときどき学生さんにコメントを求めるようにしています。
といっても、急に当てると、学生さんが萎縮してしまうので、冒頭で「今日は何年生何組から順に当てます」などと述べておきます。
それでも、スムーズにいくとは限りません。
コメントを求めても、沈黙が続くことが少なくなく、「何もなさそうですか」などと発言を促すと逆にこちらが質問され、その部分を説明して終わりになりがちです。
思考力やコメント力をつけてもらうために、ご自分の意見を言っていただきたいところなのですが、ハードルが高く感じられるのかもしれません。
私の授業スキルに原因があるのでしょうけれども、高校生までの減点型(?)教育や、あらかじめ回答が1つに決まっている試験に学生が慣れていることも遠因でしょうか。
コメントを求めるとき、こちらが唯一の正解のようなものを用意しているわけではないのですが、その点を学生さんにうまく伝えられていないのかもしれません。
他方、学生からすると、間違うことを恐れてしまうようです。
しかし、大学での学びや社会の仕事では、答えが1つだけということは、まれだと思います。
仮に教員やほかの学生と異なる考え方であっても、ご自分のコメントを聞かせて下さい、というところから始める必要がありそうです。
双方向の授業、いわゆるアクティブ・ラーニングがいかにあるべきか、ときどき考えさせられます。
なお、先の『日本経済新聞』写真で、私は後列、向かって右から3人目です。
2019年1月⑤
『外交』2019年1月号、146頁に、秋山昌廣/真田尚剛・服部龍二・小林義之編『元防衛事務次官 秋山昌廣回顧録──冷戦後の安全保障と防衛交流』(吉田書店、2018年)の短評が掲載されました。
2019年1月④
『みすず』2019年1・2月号「2018年読書アンケート」36頁に、酒井哲哉先生が『高坂正堯』の短評を載せて下さいました。
深く御礼を申し上げます。
2019年1月③
『日本経済新聞』1月19日朝刊27面に、秋山昌廣/真田尚剛・服部龍二・小林義之編『元防衛事務次官 秋山昌廣回顧録──冷戦後の安全保障と防衛交流』(吉田書店、2018年)の短評が掲載されました。
こちらにリンクを貼っておきます。
詳しい内容については、こちらに吉田書店のリンクを貼っておきます。
2019年1月②
拙著『高坂正堯――戦後日本と現実主義』(中公新書、2018年)第2刷が発行されました。
第2刷では、数カ所を修正しました。
2019年1月
謹んで新春のご祝詞を申し上げます。
本年も、ご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
追伸 数年前から、年賀状や年賀メールは取り止めております。非礼をお詫びいたします。
2018年12月⑩
拙著『高坂正堯――戦後日本と現実主義』(中公新書、2018年)の増刷が決まりました。
こちらに中公新書Twitterのリンクを貼っておきます。
第2刷が流通するのは、年明けになってしまうと思います。
今年も、同書の関係各位をはじめ、多くの方々に大変にお世話になりました。
例えば同書の終章362、364頁などに明記しましたように、高坂先生の他界については、
高坂節三『昭和の宿命を見つめた眼──父・高坂正顕と兄・高坂正堯』(PHP研究所、2000年)
同 「兄・正堯と母」(『季刊アステイオン』1996年10月号)
といった文献に依拠しています。
他界前の家族との会話や電話のくだりが、文献からの引用であり、私の創作でないことはもちろんです。
直接引用が続く場合、最後のところに出典を入れてあります。
私が高坂先生の弟子ではないだけに、それらの文献が評伝の執筆に不可欠でした。
重ねて御礼を申し上げます。